|
6月28日(金)  2階の年中T組の子たちが騒いでいる。だれかが下のテラスの屋根にカスタネットを落としてしまったらしい。「自分たちのことは自分たちで」とばかりに、クラスの子たちが空き箱などをつなげた道具で、何とか取ろうとしたが、テープがはがれて道具が落ちてしまったり…。これは年長の運動会のゲームに通じるなと思った。 物干し場の軒下にあるツバメの巣では、ひな鳥が聞き漏らすぐらいの小さな声を出していて、親が運んでくるエサをねだっている。孵化したのはうれしいが、どうも2羽しかいないようにも見える。4から5羽ぐらいが普通なのだが。  |
|
6月27日(木)  天気が回復し、大きいプールがやっとオープンした。子どもたちがはじけたのは言うまでもない。プールに供給する水が落ちてくる太いホースの下では、冷たさの中で度胸試しをするように、水を背中や頭に受ける子たちがいた。 年長児たちは「かえでの森」に出かけて七夕用の笹を2本切り、ロープにつないで運んできた。坂道を引き上げる時の女の子たちの会話「小学校へ行ったらもっとがんばらんといけんのよ」「えーっ、小学校へ行ったらこんなことせんと思うよ」。どちらもごもっとも。  |
|
6月26日(水) 国の政策の中で幼稚園ももまれている。幼保を一元化しようという新制度にどう対応するか、という研修会に参加のため、東京に出張。もちろん非常に重要な内容だし、どう対応するかは難しいところだが、つまらない政争に混ぜ返されているのも事実だ。 待機児童対策も、少子化対策も、女性の就労支援ももちろん大切だが、何よりも今の毎日を真剣に生きている子どもたちのよりよい育ちをどう保障するかが核にならなくてはならない。 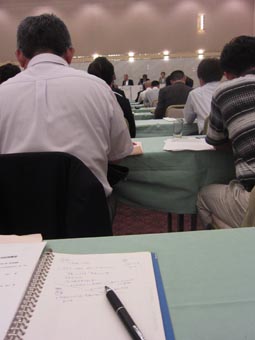 |
|
6月25日(火)  気温はやや低めだったが、今日は年長2クラスが川遊びを楽しんできた。雨続きだったので前回の年少のときに比べ水量は数倍に増えていた。しかし、最後には流れの急な所のよじ登りにも挑戦。1ヶ月限定でイタリアからやって来ているAちゃんも「負けないぞ!」 1週間前にオープンしていたはずのプールだが、雨続きでいまだに出番がない。今日の年少初プールも小さいプールだけになったが、子どもたちは結構満足の表情。水不足は困るが、暑さも待ち遠しい。  |
|
6月24日(月)  「おせっかいクラブ」の皆さんがお世話をしてくださっているアサガオの青が、雨上がりには一層引き立つ。その名も「天空の蒼」。グリーンカーテンになるのは気長に待ちたいが、名前の通り高い空を目指す勢いは感じる。しぼんだ花ではきれいな色水もでき、子どもたちを喜ばせている。 年長Kちゃんが開発したヘルメットは、目と口にふたがついている。「隕石が落ちてきたら、これをかぶってふたを閉めるの」だそうだ。間に合えばよいが。  |
|
6月21日(金)  今日も雨。年長A組では女の子たちが手芸に夢中になっていた。本物の針と糸を使うので、テーブルを囲む程度の人数だけだが、適度の緊張感もあり、いやでも集中する。 一方、外が大好きな年少児は、いつまでも室内だけでは収まらない。傘を持って園庭探検に出たR君は、テラスから落ちる雨だれが傘ではじける様子を楽しんでいた。雨の日らしい過ごし方を楽しむ年長児と、雨そのものを楽しく年少児。  |
|
6月20日(木)  大雨洪水警報のため地元の小中学校は休校。でも幼稚園はバスと保護者の送迎なので平常保育。雨の日でも子どもは実に妙な遊びを考えつく。今日はこもれびホールの三角の積木を渡って歩く遊びを開発。子どもたちは余裕の表情で渡っていくが、普段裸足で過ごしていないからか、大人は足裏が痛くて大半が途中で脱落。ちなみに私は、地獄へ落ちたときの練習だと思い、がんばって完歩。 そして子どもは「片づけだよ」の声ではなかなか動かないのに、やり始めると徹底的に掃除しなくては気がすまない人たちのようだ。  ★年1回発行の卒園生だより"Navigation"第17号を発行しました。このHP上でもお読みいただけます。「卒園生コーナー」からJumpしてください。 |
|
6月19日(水)  年長児の田植えから20日。稲はしっかり根付いているが、雑草も目立ってきたので1回目の草取り作業をする。道具は50年ぐらい前にはよく見られた「田車」というもの。最近はかえで幼稚園以外では見たことがないし、パソコンでも変換できない民俗資料館級の道具。それを21世紀生まれの子どもたちが使う風景は、愉快である。 K君Kちゃんが挑んでいるのは、昨日私が披露した、指先のキャップが消える手品。いくら気合いを入れても消えないので、またまた二人は大笑い。気合いで消えれば手品師はいらないよ。  |
|
6月18日(火)  6月の誕生会を行った。職員の出し物は「ザ・マジックショー」。職員が次々と登場して、8つの手品を披露した。われわれの腕前だから、大人から見ればネタバレのところも多いのだが、参加された保護者の皆さんは、暖かい拍手で包んでくださった。私を含む出演者は、「どうやったん?」「もう1回やって」と、終了後も子どもたちにつきまとわれることとなった。 園庭の畑では、夏野菜のオクラがきれいな花を咲かせている。ここは年長の管轄だが、サツマイモの苗を植えて以来、年少児たちも興味を深めているようだ。  |
|
6月17日(月)  アメリカからお母さんの里に一時帰国している姉妹が1ヶ月限定で在園しているが、今日はイタリアからやはり1ヶ月限定のきょうだいが入園。多少不安そうだった年長のお姉ちゃんだが、すぐに慣れたようだ。楽しみに待ち構えていたクラスの女の子たちいわく「あったしゅんかんに ともだちになったよ」 ブランコの上に枝を伸ばしているアベマキは、二十数年前、子どもたちと埋めたドングリが芽を出し育ったもの。今ではブランコに乗る子を紫外線から守ってくれる、ありがたい「先輩の木」である。  |
|
6月15日(土)  私が非常勤講師をしているH大学幼児教育科の学生を幼稚園に招いて、2コマ分の「学外授業」を行う。空梅雨の日々なのに、この時間に限っての雨。「屋根のぼりに登りたかった」「かえでの森に行きたかった」など、残念の声が聞かれた。残念なのはこちらも同じ。 でも、室内での活動は盛り上がった。「コマの5回連続回しに成功しました!もらえますか!?」「うーん、そういうわけには…。じゃあ、写真なら撮ってあげるよ」  |
|
6月14日(金)  真夏日が続き、各クラスには扇風機が出されているが、年長T組には岩手産の南部風鈴も登場し、重厚だが涼やかな音色を流し始めた。この音は結構遠くにいても聞こえるが、かといって近くで聞いてもやかましくはない、不思議な音色である。 あまりの暑さにヤケクソになったわけではあるまいが、そのT組ではホットケーキ作りが行われていた。暑くてもおいしいものを食べるのは大好きな子たちが、ホットプレートの回りに集まった。いい子たちです。  |
|
6月13日(木)  2日続いた真夏日。プールはまだ準備が整わないが、自然の川ならいつでもスタンバイだ。今年度の川遊びの先陣は何と年少組。雨不足で川の水が少ないのは、初めての年少にとってはむしろ好都合。渓谷の冷たい水に歓声を上げながら、他では味わえない気持ちの良さを楽しんだ。 暑い日には麦わら帽子がよく似合う。この夏の少年も、田んぼにいるいろいろな生き物に夢中。だがこの直後、この少年は田んぼに石を投げ入れて、私に小目玉を食らった(大目玉ではない)。 ★昨日掲載した「一反木綿」は、妖怪ではなく、ハナアブの幼虫オナガウジであろうとの情報をいただきました。間違いないと思います。ありがとうございました。  |
|
6月12日(水)  絵本や児童文学の好きな保護者で作る同好会「かえで本の森」の主催で、「今こそ昔話を」という講演をさせていただいた。内容の大半は、昔話研究家の先生の受け売りだが、昔話が絶滅の危機に瀕している今は、受け売りでもその大切さを伝えていく必要があると感じている。それが保育者としての私の役目でもあろう。だが、立ったまま、子どもの顔を見ながら、ペダル操作もしながらピアノを弾くという、S組担任のような芸当は、私にはできない。 オタマジャクシが成長してきた田んぼに現れたのは…?あっ!妖怪「一反木綿」だ!(これが何か分かる人、教えてください)  |
|
6月11日(火)  自然観察のプロ、K氏にも同行していただき、年中2クラスが「おおの自然観察の森」に出かけた。メインのモリアオガエルは雨の方が活発なのだが、曇り時々晴れという「生憎の」天気。しかし、木の枝にいたカエルも見られたし、ソフトボール状の卵塊に触ることもできた。また、道路側溝でのカエル、カメ、イモリをつかまえての観察が何より盛り上がったが、泥んこや水たまりをあえて掃除せず残してくださった森の職員の心遣いに感謝である。 香り高いササユリにも鼻を近づけてみた。すると必ず「トイレのにおい」という声が出る。現代のトイレは花園のような場所なのだ。  |
|
6月10日(月)  木の枝に卵を生むモリアオガエルなど水辺の生き物の観察のため、明日、「おおの自然観察の森」に出かける予定にしている年中2クラスが、「予習」のため「モリアオガエル」という子ども向けの映画作品を鑑賞した。期待感も大きくふくらんだようだ。 先週子どもたちが運んだプールの部品を組み立てる作業を、放課後、職員が行った。園庭の風景が一気に夏モードになった。  |
|
6月7日(金)  一昨日収穫した梅の実は、早速全クラスに分けら、それぞれが大きな瓶でジュースに漬け込む。年少H組では、子どもたちが瓶を囲み、慣れない手つきで梅の実にフォークで穴をあけていた。 そして午後は、昨日の年中、年長に続き、年少がサツマイモの苗を植えた。「畝と並行に」「細長い穴を」「葉っぱは埋めないで茎は埋める」など、言葉で作業の説明をするのは難しいが、職員が実演しつつ、何とか終了。初夏は農作業が忙しい。  |
|
6月6日(木)  園庭の畑に、年中、年長組がサツマイモの苗を植えた。今年から畑が拡張されたので、1クラスの担当分も多くなった。植えた後じょうろで水やりをするAちゃん。水をまんべんなくまこうとする気持ちが、じょうろを持たない手に表れている。 未就園児親子の自由登園日「かえでっこくらぶ」が今年度も始まり、昨日と今日で計110組以上の親子がやって来た。終了した午後、年長の女の子2人が「あーあ、やっと『かえでっこ』が終わったね」とホッとしたようにため息をついた。園児たちも気を遣いながら遊んでいるのだ。  |
|
6月5日(水)  南側の斜面にある梅が実ったので収穫した。まず年少から始め、年中、年長の順で取っていく。難しいところが残っていくから、ちょうどいい。でも一番たくさん収穫するのも年長である。やはり技術、集中力、そして連携力が格段に伸びるからだ。取った梅は、クラスごとにジュースに加工する。 定期健康診断の2日目。今日は年少が登場。ちょっとドキドキした顔、こわそうな顔になる子も多いが、園医のK先生の柔らかい雰囲気で、だんだん平気な顔になってくる。  |
|
6月4日(火)  自分たちで環境作りにかかわることを大切にしているかえで幼稚園では、夏に使うプールの部品も子どもたちで運ぶ。大きい子と小さい子をミックスし、時には10人以上のメンバーで気持ちを合わせて運ぶ。「小さい子に合わせて動いてね」と言うと、年長児は「任しとき」という顔になる。汗がにじみ出るころ、作業は終わった。 年長A組の積木コーナー。ビー玉のコース作りはますます高度化し、最近は玉が空中を飛んで次の穴に入るというアクロバティックな装置までできている。しかも成功率が結構高い。興味の深まりに応えられる環境が大切だ、と、当たり前のことだが、つくづく感じる。  |
|
6月2日(日)  今年度初の親子参加行事「みんな子どもデー」を行い、雨の中、園内は多くの親子でにぎわった。年中2クラスは、6家族1グループで大きな押し寿司に挑戦。家族ごとに工夫された具が、きれいな彩りになった。 年長2クラスは恒例のそうめん流し。お父さんたちが雨の「かえでの森」に降り、4本の太い竹を切ってきて水路を作ってくださった。屋根の下という制約のため例年より小規模な水路しかできなかったので、1クラス3分ずつの交代制で食べた。大変だったが、雨にもめげなかったそうめんは、格別の味だったのではないだろうか。  |